発電の仕組み
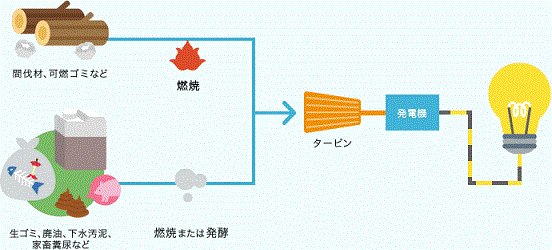
電気を作る仕組みは火力発電とよく似ています。ボイラーで燃料を燃やすことで水蒸気を作り、その水蒸気の力で発電タービンを回すという流れです。ですので、電気を作るまでの流れに関しては、火力発電と同じと言えます。
- ボイラーで燃料を燃やす
- 燃やすことで発生する熱を利用して水を熱する
- 熱された水が沸騰して水蒸気を作る
- 出てきた水蒸気が発電用のタービンを回す
簡単にまとめてしまうと、上の4つの手順から成り立っています。学生時代の理科の授業などで習ったことがあるという方も多いのではないでしょうか。
そして、バイオマスとは有機資源のことを指します。植物・廃材・生ゴミ・下水・動物の排泄物などといった様々なものが有機資源に含まれます。
これらの有機資源は枯渇することがないため、風力発電や地熱発電などといった自然のエネルギーを用いた発電方法と同様に、バイオマス発電は再生可能エネルギーに分類されています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 再生可能エネルギー | 資源の供給不足の可能性 |
| 二酸化炭素(CO2)の中立性 | 土地利用の競合 |
| 廃棄物の有効活用 | 収集・輸送コスト |
| 地方経済の活性化 | 効率の低さ |
| エネルギー自給率の向上 | 環境への影響 |
| 安定した電力供給 | 二次汚染のリスク |
| 多用途利用 | インフラ整備が必要 |
| 環境保全効果 | 廃棄物処理の問題 |
| 炭素固定機能 | 競争力の課題 |
| 技術革新の促進 | 季節性や品質のばらつき |
バイオマス発電のメリット
上の表に出てきた各メリットについてかんたんに解説します。
再生可能エネルギー
バイオマス発電は、植物や動物由来の有機物を原料とするため、再生可能エネルギーとして分類されます。これらの原料は、自然界で循環的に生成されるため、化石燃料のように枯渇するリスクがありません。農作物の副産物や林業残材、食品廃棄物、家畜糞尿など、多様なバイオマス資源が利用可能で、持続的な供給が期待できます。この特性により、長期的なエネルギー供給の安定性を確保でき、持続可能な社会の実現に寄与します。
二酸化炭素(CO2)の中立性
バイオマス発電では、燃焼時に排出される二酸化炭素が、原料の植物が成長過程で吸収した二酸化炭素量と相殺されるとされています。このため、理論上は大気中のCO2濃度に大きな影響を与えません。この炭素中立性が、地球温暖化を抑制する取り組みにおいて重要視されています。ただし、燃焼プロセスや輸送で発生するCO2を抑えるため、効率的な技術と管理が必要です。
廃棄物の有効活用
バイオマス発電は、農業廃棄物や食品廃棄物、林業副産物など、通常は廃棄される有機物をエネルギー源として活用できます。これにより、廃棄物の量を削減し、環境負荷を軽減します。また、廃棄物がエネルギーとして再利用されることで、循環型社会の構築に寄与します。適切な処理技術が導入されることで、廃棄物を単なる負担から価値ある資源へと転換できます。
地方経済の活性化
バイオマス資源は地域ごとに異なる特性を持ちます。そのため、地域で利用可能な資源を活用することで、地元の産業や雇用を支援できます。例えば、農業地域では作物残渣、林業地域では伐採残材が活用されます。これにより、エネルギー供給と地域経済の強化が同時に進められます。地方自治体や企業の協力が求められますが、地域活性化の重要なツールとなり得ます。
エネルギー自給率の向上
バイオマス発電は、国産のエネルギー源を利用するため、エネルギー自給率の向上に貢献します。輸入化石燃料への依存を減らし、エネルギー安全保障を強化できます。特にエネルギー価格が不安定な国際市場において、国内資源を活用することは経済的な安定性をもたらします。地域で生産・消費されることで、エネルギーの地産地消も実現可能です。
安定した電力供給
太陽光発電や風力発電と異なり、バイオマス発電は天候に依存しません。バイオマス原料が安定的に供給される限り、24時間稼働が可能です。この特性により、電力供給の安定性が確保され、再生可能エネルギーの一部として重要な役割を果たします。エネルギーの安定供給が求められる地域や産業に適しています。
多用途利用
バイオマス資源は、発電だけでなく、熱供給や液体燃料(バイオディーゼル、バイオエタノール)としても利用できます。これにより、電力だけでなく、輸送や暖房分野にも応用が可能です。エネルギー利用の多様性が広がることで、各分野における化石燃料依存を減らす手段となります。これらの技術は進化しており、より効率的な利用が期待されています。
環境保全効果
バイオマス発電は、森林管理や農業廃棄物の削減に寄与します。例えば、伐採残材の利用は、森林火災のリスクを減らす効果があります。また、適切に管理されない廃棄物が放置されることで発生するメタンガスなどの温室効果ガスを抑制することもできます。環境保全とエネルギー生産を両立できる点が特徴です。
炭素固定機能
特定のバイオマス技術(例えば、バイオ炭)では、炭素を土壌や他の形で固定することが可能です。これにより、土壌の肥沃度を高めながら、炭素の大気への放出を抑制します。これらの技術は、農業や林業と組み合わせることで、持続可能な環境管理を実現できます。
技術革新の促進
バイオマス発電は、バイオ燃料やバイオ化学品の研究開発を通じて、新たな技術革新を促進します。特に、効率的なエネルギー変換技術や炭素中立を実現するプロセスの開発が注目されています。これらの技術革新は、再生可能エネルギー全体の発展に貢献し、持続可能な未来を形作る基盤となります。
バイオマス発電のデメリット
上の表に出てきた各デメリットについてかんたんに解説します。
資源の供給不足の可能性
バイオマス発電は原料となる有機物(農業廃棄物、林業残材、食品廃棄物など)が必要ですが、その供給量には限りがあります。特に、需要が急増した場合や、特定地域で大量のバイオマスを利用する場合、資源の枯渇や不足が懸念されます。さらに、供給不足が進むと価格が上昇し、採算性が悪化する可能性もあります。また、適切に管理されないと持続可能性が損なわれ、森林伐採や土壌劣化といった環境問題が生じる恐れもあります。そのため、バイオマス発電を拡大するには、安定供給のための長期的な資源管理計画や、効率的な利用技術の開発が求められます。
土地利用の競合
バイオマス燃料用作物(トウモロコシ、サトウキビ、パーム油など)の栽培が食料生産と競合する問題があります。特に、食料不足が深刻な地域でエネルギー作物栽培が優先されると、食料価格が上昇し、貧困層に影響を及ぼす可能性があります。また、大規模な単一栽培(モノカルチャー)は生物多様性の喪失や土壌の栄養分低下を引き起こすことがあります。これらの課題を克服するには、非食用バイオマス(廃棄物、海藻、非耕作地用作物など)の活用や、耕地面積を増やさずに収量を向上させる農業技術の導入が必要です。
収集・輸送コスト
バイオマス資源は広範囲に分散しており、その収集と輸送にかかるコストが高いのが課題です。例えば、木材や農業廃棄物などは収穫後に発電所まで運ばれる必要がありますが、そのプロセスでエネルギー効率が低下する場合があります。また、輸送距離が長い場合には、化石燃料を使用する輸送車両からの排出ガスが増えることも環境的な問題となります。これを解決するためには、地域密着型の小規模バイオマス発電所の設置や、収集効率を高めるための専用インフラの整備が重要です。
効率の低さ
バイオマス発電は、燃料のエネルギーを電力に変換する効率が他の発電方式に比べて低い場合があります。特に、燃焼を利用する方式では、エネルギー損失が発生しやすいです。これにより、発電コストが高くなるだけでなく、原料の大量消費を必要とするため、資源利用の効率が課題となります。新技術の導入や発電プロセスの最適化によって、エネルギー変換効率を向上させる努力が求められています。また、廃熱利用(コージェネレーション)などの工夫によって、全体のエネルギー効率を高める取り組みも重要です。
環境への影響
バイオマス資源を大量に消費することで、環境への悪影響が懸念されます。例えば、森林伐採が進むと、生態系のバランスが崩れ、土壌浸食や水源の枯渇につながる可能性があります。また、過剰な農業廃棄物の利用は、土壌の栄養分を奪い、土地の劣化を引き起こすリスクがあります。これらの問題を防ぐには、バイオマス資源の持続可能な収穫や管理が必要であり、再生可能資源の範囲内で利用を制限する政策が重要です。
二次汚染のリスク
バイオマスを燃焼させる際、不完全燃焼や不適切な処理が行われると、有害な物質(微粒子、硝酸化合物、ダイオキシンなど)が発生するリスクがあります。これにより、大気汚染や健康被害が懸念されます。また、発電所の排出ガス処理技術が不十分な場合には、地域の環境に深刻な影響を与える可能性があります。この問題に対処するためには、高度な排出ガス浄化技術の導入や、燃焼プロセスの改善が必要です。
インフラ整備が必要
バイオマス発電を効率的に運用するためには、専用の発電施設や輸送インフラの整備が不可欠です。これには初期投資がかかり、特に小規模な地域や発展途上国では資金不足が課題となることがあります。また、発電所周辺のコミュニティとの調整や環境影響評価の実施にも時間とコストが必要です。これらを乗り越えるためには、政府や民間セクターの連携による資金援助や政策支援が重要です。
廃棄物処理の問題
バイオマス燃焼後に残る灰や副産物は、適切に処理しないと環境問題を引き起こす可能性があります。例えば、灰には重金属が含まれることがあり、不適切な処理は土壌や水質汚染につながります。一方で、これらの廃棄物を肥料や建築資材として再利用する技術もありますが、追加コストが発生することが課題です。このため、廃棄物を無害化しつつ有効活用する方法の確立が求められます。
競争力の課題
バイオマス発電は、化石燃料や太陽光、風力発電に比べて発電コストが高い場合があります。特に、資源の収集や輸送、燃焼後の廃棄物処理にかかるコストが全体の競争力を低下させています。これを克服するには、技術革新によるコスト削減や、政策的な補助金やインセンティブの導入が求められます。また、バイオマス発電の副産物(熱や燃料)の販売を通じて収益性を向上させる取り組みも必要です。
季節性や品質のばらつき
バイオマス資源は、季節や地域の条件によって供給量が変動するため、安定した供給が難しい場合があります。例えば、農作物や林業残材は収穫期に集中し、それ以外の時期には供給不足になることがあります。また、原料の品質が一定でない場合、発電効率や燃焼プロセスに影響を与えることもあります。この問題を解決するためには、原料の長期保存技術や、安定供給を可能にするバイオマス管理体制の構築が求められます。
火力発電との違い
これで火力発電とバイオマス発電が同じ仕組みを利用して電気を作っているということが分かりましたが、それではなぜバイオマス発電は自然エネルギーに分類されているのに対し、火力発電はそうではないのでしょうか。
その答えは「燃料」にあります。上の手順の1番のところに「燃料を燃やす」と書いてありますが、実はバイオマス発電と火力発電とでは、利用している燃料が異なるのです。この燃料の違いが自然エネルギーか否かを分けています。
バイオマス発電で使用する燃料は「バイオマス」です。一方で、火力発電で使用される燃料は化石燃料(石炭・石油・天然ガスなど)です。
化石燃料は燃やすと多くの二酸化炭素を排出しますが、バイオマスにはカーボンニュートラルという考え方ができるため、二酸化炭素を増加させないという特徴があります。
つまり、カーボンニュートラルとは「二酸化炭素を増加させない」という考え方を意味します。
これは、バイオマスは燃料として燃やされる際に排出する二酸化炭素と同じ量の二酸化炭素を、燃やされるまでに吸収してきているため、結果的に大気中に存在する二酸化炭素の量は変わらないという考え方です。
バイオマスの種類
バイオマスとは「枯渇の恐れがない生物資源」のことです。再生可能資源の一種と解説されることもありますが、このままでは何を指すのかよく分かりませんので、次に種類別に具体的な資源を挙げてみたいと思います。
| 廃棄物系 | 廃棄物系バイオマスとは、工場や一般家庭などから大量に出る資源を指します。具体的には「木屑・生ゴミ・紙・家畜の糞尿・食品廃材・下水汚泥」などのことです。 |
|---|---|
| 未利用系 | 未利用系バイオマスとは、他にあまり使用用途のない資源を指します。具体的には「稲わら・麦わら・もみがら・野草・間伐材・被害木」などのことです。 |
| 栽培作物系 | 栽培作物系バイオマスとは、作物を由来とした資源を指します。具体的には「さとうきび・てんさい・トウモロコシ・菜種・落花生」などのことです。 |
推進派と反対派
ここまで、バイオマス発電の仕組みとメリットデメリットについてご紹介させて頂きましたが、ここからはそのメリットデメリットを踏まえた上で、バイオマス発電に対してどのような意見が出ているのか、ご紹介したいと思います。
賛成意見
コストの問題もいずれ解決できる
食料となり得る穀物等を原料とする方法を除けば、バイオマス発電には賛成です。特にこれまで廃棄されていた廃材、間伐材、糞尿などを原料としたバイオマス発電には大賛成です。
福島原発事故は、大変不幸な出来事ではありましたが、国民一人一人が真剣にエネルギー問題を考える機会を与えてくれました。
大規模で危険な原子力発電ではなく、自然のサイクルに逆らうことなく、人にも環境にも優しい小規模なバイオマス発電所を、自治体単位で設置してゆくのが理想的な形です。
コストが高いという反対意見があります。しかしそれはバイオマス発電が未だ社会のシステムとして一般的に稼働していない為です。
今後、廃棄物を利用したバイオマス発電を本格的に主要な発電の一部として導入すると決めれば、もっと効率の良いシステムが構築される筈です。
そもそも原料となりうる廃棄物を処分するにも、これまでコストが掛かっていた訳で、それを考慮すれば非現実的にコストが高い訳ではないと思われます。
自治体の中でも原料の調達が可能で、何より安全性という意味でも、今後優先して実用化を進めるべき発電方法であるべきです。
廃棄物の再利用は大きな魅力
バイオマス発電に賛成します。理由は、発電方法は色々なものを用意しておいた方がよいと思うからです。
発電方法を一つだけに絞ったり種類が少なかったりすると、その発電方法がダメになってしまった時に代替手段を用意するのが難しくなってしまいます。
また、バイオマス発電では廃材や木屑を燃料として使えるところも魅力的です。工場などでは大量の廃棄物が出るので、それらを有効利用できるのは大きなメリットだと思います。
廃棄物を処理するのにも大きな費用がかかるので、その廃棄物を発電に利用できるなら利用した方が良いと思います。
バイオマス発電がもっと一般的になれば、研究も進んで効率的な発電が可能になるはずです。発電方法は既に色々ありますが、バイオマス発電というものを知っている人はまだそれほど多くはないと思います。
バイオマス発電も発電方法の選択肢の一つとして、しっかりとした研究をしていくべきだと思います。
安全性の観点からも賛成
私の住んでいる福島県では、原発を廃止しようという動きが高まっております。代わりに太陽光発電所や風力発電所がたくさんでき、さながら自然エネルギー発電の先進県になりつつあります。
その流れの中でも、カーボンニュートラルという考えから、バイオ燃料による発電も研究が進んでいます。バイオ燃料ということで植物から精製できたり、不用品を利用できたりと、ゼロエミッションという観点からもいい試みだと思います。
それに最近は稲作も制限されるようになり、休田が目立つようになり、見ていて「勿体ない、バイオマス燃料でも作ればいいのに」と思ってしまいます。
植物を燃料にするということで、燃やしても土に帰り、また育てば燃料になるという永久的なサイクル燃料です。それに原子力のような、いざとなるととても危険な燃料では無いため、安全性の観点からも賛成です。
資源の有効活用
私はバイオマス発電に賛成です。バイオマス発電は家庭などからでる生ゴミや木くずなどを燃やし、その際に発生したエネルギーでタービンを回し発電します。
現在主流になっている化石燃料を使用した発電は、大量の二酸化炭素を排出してしまうため、地球温暖化などといったように環境へ悪影響を与えてしまいます。
しかし、バイオマス発電はカーボンニュートラルですので、二酸化炭素の増加を抑えることができます。
しかも、生ゴミや木くずといった普段ならゴミとしてそのまま廃棄してしまうものをエネルギーとして使っているため、無駄なく有効活用することができます。
このように、バイオマス発電は従来の化石燃料の発電よりも環境にいい事から、私はバイオマス発電に賛成します。
より効率的にしていくことは可能
再生可能エネルギーとして注目を集めているバイオマス発電ですが、現在のところ、全発電量にしめるバイオマス発電の割合はごくわずかな状態です。
東日本大震災以降、原子力発電への安全性が疑問視され、主力は火力発電となっていますが、火力発電の燃料となる石炭や石油にはかぎりがあります。すぐになくなるというものでもありませんが、必ずなくなる日がやってくるものです。
そういった意味で、バイオマス発電の再生可能という点は燃料の確保という面において重要性があるのではないでしょうか。
まだまだ歴史の浅いこともあり、発電効率や経費面で改善していかなければいけない点はあるとは思いますが、技術革新によって、より効率的にしていくことは可能だと思います。
現在の電力事情だけでなく、将来的な電力事情を考慮したうえで、こういった再生可能エネルギーによる発電量を増やしていく必要があるのではないでしょうか。
もっと普及させるべき
かぎりある資源を有効に使うという点では、全面的に賛成です。特に生ゴミや下水汚泥や糞尿などを発酵させるバイオガスによる発電は、燃料の安定供給が見込めるはずですので、もっと普及させるべきだと思います。
ただし、ニオイの問題や、有害ガス・物質の漏えいなど、設備周辺地区への悪影響が心配ですし、万が一の事故のときの衛生的な問題は必ずクリアしておくべきです。
また、可燃ごみや廃油を用いた直接燃焼方式もいいと思います。ただ、それだけでは発熱温度が低くなるのは否めないので、木材クズが大量に必要とされます。
しかし、今日では木材クズを再利用する技術も高まっているので、できるだけ木材を燃やさずに済む方法が開発されることを望みます。
有効活用してほしい
バイオマス発電についてですが、これを、ゴミの処理を利用した発電という意味で捉えるならば、この発電には賛成です。私はスーパーマーケットなどの倉庫で、何年間かアルバイトをしたことがありますが、そこでは毎日大量にゴミが出ます。
倉庫からでるゴミで、ダンボールであれば、持ち帰って自分の家で利用できるかもしれませんが、荷物がかなりかさばり、個人が持ち運ぶのはかなり大変な量です。そのため、結局、ゴミ収集の業者さんなどに持って行ってもらうしかありません。
ですが、毎日大量のゴミが出るということは、毎日安定した量のゴミが出るとも言えます。そうなると、毎日安定したバイオマス発電の発電量が確保できると考えられます。
実際にアルバイトで大量に出るゴミを見てきた人間としては、バイオマス発電を有効活用してほしいです。
とてもすばらしい
私はバイオマス発電に賛成です。理由はバイオマス発電は再生可能な火力発電ともいえるからです。バイオマス発電は、生ごみや木くずといったゴミとなってしまうものを燃やして電力を発電します。
火力発電の原料となる石油や天然ガスの代わりに、私たちが普段の生活で排出するものを燃やしてエネルギーにできるのは、地球環境の面から見て、とてもすばらしいと思います。
今はまだコストがかかるなどといったデメリットのためにあまり普及は進んでいませんが、日本は火力発電大国です。
火力発電のために培った効率のいいエネルギー変換方法を、バイオマス発電にも活かすことで、コストダウンできるのではないかと考えています。
他の再生可能エネルギーに比べて、現状の発電方法と似たような仕組みで発電できるといった理由で、バイオマス発電はどんどん普及させるべきだと思います。
エコフレンドリーなエネルギー
バイオマス発電で一番のメリットは、やはり再生可能エネルギーだという事ではないでしょうか。
リサイクル的な観点から、環境にも優しく、私たちが毎日生産し、なおかつ処理に困っているゴミを有効活用できる、今大変注目されている発電方法です。
自分たちでつくりだすごみを使用するので、他の国の資源に頼る必要がなく、安定した供給が望めます。何かを消費したり、危険が伴ったりしない、大変エコフレンドリーなエネルギーの生産の仕方だと思います。
これからは何をするにも環境への配慮が叫ばれる時代です。そんな今に時代にぴったりなグリーンな発電方法ですから、これからも技術が発展してどんどん広まっていくことを期待します。
小規模なバイオマス発電をあちらこちらに
自然環境に優しいバイオマス発電には全面的に賛成します。3.11の福島原子力発電所の事故以降、日本でも今後のエネルギー政策が最重要課題として注目を集めています。これまで安全で安価とされてきた原子力発電が、実は大変危険なものであるだけでなく、経済的にも大変高コストである事が明らかになりました。
そもそも電気とは、人が豊かで幸せな生活を営む為に必要とされるエネルギーの一つであり、その全てが必ずしも電気である必要はありません。また、電気を発生させるにも、その手段が原子力を使ったものである必要は全くありません。
原子力発電の結果発生する危険な使用済み核燃料の処理方法も決まらず、また明らかに福島の事故も終息していないにもかかわらず、当事者である日本の原子力発電継続の判断は、日本がもはや正常な判断を下せる国家ではないことを世界に知らしめてしまったのではないでしょうか。
日本という国は、そもそも自然災害や環境にも上手に対応していた国でした。そのような国が、バイオマス発電に必要な原料や先端技術も持っているにもかかわらず、尚も原子力発電を続けるということは、自然や地球に対する冒涜以外の何物でもないと思います。
今後は、もっと小規模な地域単位でのバイオマス発電を強化することで、新たな産業と雇用を創出すると同時に、災害に強く安全なエネルギー政策を進めるべきと考えます。バイオマス発電を始め、風力発電や地熱発電など、再生可能エネルギーを利用した発電をもっと増やしてほしいです。
ゴミ問題も一緒に解決できる
私がバイオマス発電に賛成する理由は、余っているものと足りないものを上手く組み合わせた発電方法だと思うからです。
言ってみれば、小池都知事か都政において実行しているやり方です。空き家対策と保育園の不足、余っている空き家を利用して足りない保育園に充てる。そんなやり方に似ています。
畜産業が盛んで、人の数よりも牛や豚などの家畜の数のほうが多い地方では、家畜の糞尿の処理が大変だと思います。そして、原子力発電に頼らないエネルギー政策へ変換していくのであれば、再生可能エネルギーの発電量はまだまだ足りない状態です。
バイオマス発電は、この二つを組み合わせて両方の問題を解決できるスマートな発電方法だと思います。バイオマス発電のための木材チップを作るために、新たに森林を伐採するなどしないようにすれば、バイオマス発電は環境にも優しい発電方法になると思います。
新しいエネルギーとしての期待
バイオマス発電は、今後期待されているエネルギーの中でも画期的なものでしょう。なぜなら、ただそこにある自然を利用するというわけでもありません。今までゴミとして捨てられるようなものも利用できる可能性があるからです。
従来型の発電は、必ず自然環境にダメージを与えたり、環境を悪化させていくようなものでした。しかし、バイオマス発電は、発電とはまったく別の廃棄物の問題まで一緒に片づけてしまうことができるのです。
今まで廃棄されるだけのものを発電のエネルギーとして再利用できるということは、画期的なことなんです。
コストがかかるとは言われていますが、クリーンなエネルギーを使うためにはそれ相応のコストを負担すべきだとも言えます。また、今後技術が発展してに従ってコストも低くなっていくでしょうし、普及していけばさらに下がっていくものと考えてよいのではないでしょうか。
ちょっとした意識の変化で、そういった新しいエネルギーを取り入れることができると思うと、未来にも希望が持てますね。
デメリットが少ない
私は、バイオマス発電に賛成です。その理由は、バイオマス発電がカーボンニュートラルという考え方に基づいて行われているからです。バイオマス発電では、燃焼させる燃料を、主として植物や木に依存しています。
物を燃やせば当然二酸化炭素が発生しますが、バイオマス発電の場合燃料が光合成により二酸化炭素を吸収するので、発生した二酸化炭素と吸収した二酸化炭素が相殺し合います。その結果、バイオマス発電では、理論上は二酸化炭素が発生せず、地球環境に優しい発電方法になるのです。
今現在、地球温暖化がデータ上からも明らかに進行している中、バイオマス発電は、救世主になりうる発電方法だと思うのです。
現在の主流な発電方法である火力発電は二酸化炭素を大量に放出しますし、原子力発電は放射性廃棄物の処理が問題視されています。そんな中でバイオマス発電は、デメリットの少ない有望な発電方法なのです。バイオマス発電がさらに普及することを望みます。
ゴミからエネルギーを作れる
バイオマス発電については、基本的に私は、賛成です。資源の少ない日本では、電力を安定的に確保するには、色々な発電システムを利用することが良いと思います。火力・原子力・水力、その他の発電システムの一つとして考えると良いと思います。
日本は、木材加工カスや家畜の糞車が非常に多い社会なので、廃油や穀物のカスなどの廃棄物を有効に利用することにより、ただのゴミからエネルギーを取り出せるのは、大変効率が良く、ゴミの再利用ができて環境にも優しいことだと思います。
核燃料を利用する原子力発電について、福島の惨事を見て反対するのはわかるが、バイオマス発電に反対する意味が私には全く理解できません。現在技術が発達して、今迄はただ捨てるだけのゴミだったものから新たなエネルギーを取り出せるのは、革新的だと思います。
ただ、家畜の糞や廃油を利用するにあたっては、周りの住民に十分配慮する必要があると思います。家畜の糞に対しては、衛生面に配慮が必要だし、廃油の場合はガス爆発等の安全面に配慮が必要です。
カーボンニュートラルの魅力
バイオマス発電には賛成の立場です。再生可能エネルギーであること、カーボンニュートラルであることがその主な理由です。
私は東北出身で、東日本大震災の際は宮城県におり、被災しました。幸い私も家族もケガひとつなく、家屋も損傷しませんでした。しかし、福島第一原発の近辺に住んでおられる方のことを考えると、地震大国である日本に、たくさんの原子力発電所を設置することに大いに疑問を感じるようになりました。
原発でない発電システムであり、かつ環境にも良いというのであれば、バイオマス発電に反対する理由はありません。特に、戦後たくさん植えられて放置されている杉林などを有効活用できる木質バイオマス発電は、大いに活用すべきです。
バイオマス発電のデメリットとして、コストがかかる、エネルギー変換の効率が悪いということが挙げられます。コストについては、技術が発達することと、バイオマス発電が主流になり、需要が伸びることでコストダウンが可能です。
エネルギー変換率の悪さは、例えば発電時に発生した熱を発電に再利用する等で、ロスを軽減することができます。
循環型社会を実現できる
自分はバイオマス発電には賛成です。なぜ賛成かというと、捨てるしかなかった木材や動物の糞尿をエネルギー源にできるからです。
日本はエネルギー資源には乏しい国です。日本国内で摂取できるバイオマスを使った発電方法は、各地で今まで捨てていた物を国内の資源として採取できるので、地域活性化にも貢献しますし、捨てる物からエネルギーを取り出して、そこからまたエネルギーを生み出すという循環型社会を実現できます。
バイオマス発電の魅力は他にもあり、安定した発電ができることです。バイオマス発電は火力発電と一緒の技術が利用されているので、同じように安定した電力を生み出す事ができます。
導入コストを考えても、日本国内で発電できる数少ないエネルギー資源ですし、世界中で地球温暖化と言われてる昨今には、最適で必要なエネルギー資源だと思います。
もっと普及してほしい
バイオマス発電は、それまでは単純にゴミとして焼却処分されていたものから電力を得る発電方法であり、とてもエコな発電方法です。
例えば、建築廃材や農業で出るもみ殻、動物の糞尿などは今まではすべて焼却処分にするほかはなく、単純にCO2を排出するだけの存在でした。しかし、バイオマス発電を導入することでこれらのゴミから電力を得ることができるようになるのです。
本来、バイオマス発電の原料は焼却処分されるものがほとんどですから、バイオマス発電の原料にしてもCO2の排出量は変わりません。これほどエコな発電方法があるでしょうか。
しかも人間が生活する限り、バイオマス発電の原料は何かしら必ず生まれてきます。新たな燃料資源を採掘しなくてもよいことを考えてみても、バイオマス発電は明らかにエコで地球にやさしい発電方法だと思います。
以上のことから、私はバイオマス発電に全面的に賛成しています。このバイオマス発電がもっと日本に普及することを祈っています。
反対意見
結局コストがかかりすぎる
バイオマス発電は家畜の廃棄物や植物などを原料にした燃料を使って発電することです。これはCO2が植物によって循環されるため、結果排出されるCO2が等しくなるという考え方から環境にやさしいという意味で注目されているようです。
しかし、この植物を育てる段階で石油などの燃料を使ってしまうと、結局排出されるCO2が上回ってしまうという問題があります。
もうひとつ問題なのは植物を耕作する土地の問題です。十分な燃料を生産するためには、広大な土地が必要になります。それを確保するために山や熱帯雨林などを切り開いてしまっては何の意味もありません。
もっと言えば、食物にもできるトウモロコシやサトウキビなどを使っていては、食糧問題にも結びつきかねません。
最後はやはりコスト面でしょうか。燃料を生産することからはじめるのですから、発電コストはかなりのもので、とても採算の合うようなものとは言いがたいです。
以上のことからバイオマス発電はまだ問題点が多く、導入は時期尚早と言わざるを得ないと思います。
別の自然エネルギーに力を入れるべき
経済的観点からバイオマス発電に反対します。バイオマス発電は単純に採算が取れないからです。日本政府は2002年に国家プロジェクトとしてバイオマスの利用を促進しました。結果はどんなものだったでしょうか。
総務省行政評価局の評価によると、データが取れたバイオマス発電のうち、7割が赤字でした。そのうち4割に至っては、バイオマス原料すら充分に調達する事ができなかったそうです。
政策評価的には「期待された効果は皆無」。この言葉がバイオマス発電の現状を端的に表しているのではないでしょうか。言い方はあれですが、要するに、壮大な税金の無駄遣いだったのです。
バイオマスの致命的な欠点として、燃焼させる為のエネルギー量が圧倒的に少ない事があげられます。
重油なら1キロあたり1万キロカロリーの発熱量がありますが、バイオマス(木質ペレット)の場合、その半分以下。わずか4,000キロカロリーの発熱しかありません。
重油なら1キロで済む所を、同じ熱量を得るためにはバイオマス2.5キロ必要になります。これでは採算が取れる筈もありません。
バイオマス発電を推進すると、電気代はより高騰し、国内産業の国外への脱出はさらに加速してしまうのではないでしょうか。同じ自然エネルギーなら太陽光発電や風力発電に力を入れてほしいです。
伸びるように思えない
バイオマス発電は、生物由来の再生可能な物質を使って発電するため、環境に優しいイメージがあります。しかし、その量が限られている以上、主要な発電として使うことができません。
このために、小規模な発電所しか作れなくて、補助的なエネルギー源にしかなりません。2017年度では総発電量の1.5%しかなく、腹の足しにもならないのです。環境を大切にしている人が趣味で行う領域から脱していません。
コスト的にも採算が取れていません。どれだけ研究が進んでいても、コスト高が続いています。発電所を建設しても、発電に使う材料にも困るところが出ています。
そのため、バイオマス発電をどれだけ頑張っていっても、伸びるように思えません。より現実的な発電方法に力を注いだ方がいいです。
小規模レベルにとどまる
基本的に廃棄素材を利用するといっても、大規模にしようとすれば必然的にコストがかかりやすい構造になっているのが問題であります。廃棄物を集めるのにも、かなりの量を必要としますので、集めるだけでもコストが大きいです。
また、自然にやさしいとは言われますが、バイオマスの燃料を作るために森林伐採をして農地を作ったりすれば、CO2を吸収するものを減らすことになってしまい、かえってよろしくないような意見があります。
食糧を生産する土地を燃料用のものを生産してしまったりもすれば、食糧戦争も起こったりもする可能性があります。
発電効率もそこまで大きくないという面からも、あまり代替エネルギーとしては有用性はなく、小規模レベルにとどまるくらいにしかならないでしょう。
日々の食事に悪影響をおよぼす可能性
バイオマス発電はコストがかなりかかります。発電所建設にはもちろんのことですが、設備自体も高額になります。
発電時に排出される二酸化炭素自体は極めて少ないので(カーボンニュートラルのため)、クリーンな発電と考えがちですが、その発電所を作るまでにも多量のCO2がでてしまうのです。
また、バイオマス発電の資源は木材や生ごみ、動物の糞等と我々が普段捨てているものを再利用しているのでエコといえばエコなのですが、エネルギーをさらに多く生産しようとするあまり、バイオマス発電に使う為だけのトウモロコシなどの食料を生産するということが起きてしまう可能性があります。
これは私たちの日々の食事に影響をもたらしかねません。こういった点をトータルしてバイオマス発電には反対です。
メインとしては無理
私は効率の悪さからバイオマス発電には反対の意見です。正確に言えば、バイオマス発電自体に反対しているのではなく、「バイオマス発電をエネルギーのメイン発生源にしよう」という意見に反対です。
バイオマス発電を推進している人たちは本当に調査したうえで言っているのでしょうか?それとも、ただ現在のエネルギー政策に対する批判として言っているのでしょうか?
おそらく後者の部分が大きいのではないでしょうか?それはただの政策批判の道具にしかすぎません。
バイオマス発電は原子力発電や火力発電と比べれば自然にやさしいエネルギーかと思います。しかしおそらく、バイオマス発電だけですべての、またはメインとして地球上のエネルギーをまかなう事は今の時点では不可能でしょう。
間伐材や不要になって他に使い道がないものだけを資源として使い、他の方法に対するサテライトという位置づけとして、その他の環境によくない発電方法を少しでも減らしていくべきだ、という観点から利用するのであれば賛成できると考えています。
二酸化炭素を増やす
木質チップを直接燃焼して発電するのであれば、反対です。
燃焼させることで、樹木が成長過程でせっかく吸収した二酸化炭素を再び大気中に放出することになり、また発電施設の建設から運転、廃止までのライフサイクルで考えれば、木質チップの直接燃焼では結局のところ大気中の二酸化炭素を増やす結果となります。
近年は二酸化炭素を吸着して貯蔵する技術や、再生可能エネルギーを使って二酸化炭素を分解する技術の開発も進められていて、このような技術が確立、進歩していくと思われます。
現時点では、石炭などの化石燃料を燃やして発電するよりはいいのだろうが、技術の発展などのブレークスルーにより、将来的には経済的にも、また地球温暖化防止の観点からも、他の発電方式の方が優位になると思います。
燃料の安定確保が非常に困難
日本では、現在242万kW容量の発電設備が認定されています(資源エネルギー庁のデータ)。ただ、このほとんどが石炭等他の燃料も使用した混合型の設備となっています。
その理由は、「バイオマス資源を安定的に入手できない」という問題点にあります。バイオマス資源は家庭から出る一般ゴミの他、廃油や木材の木くず等が原料となります。
ゴミの廃棄という点では効果がありますが、これらが常に一定量確保されるということは非常に困難です。
また、これらの資源を直接燃焼させエネルギーを取り出す場合、燃焼のための燃料が必要になります。エネルギーコストとしてはあまり効果が望めません。
バイオマス資源を発酵させる場合でも、その保管場所、発酵させるための熱源などの問題も生じます。そのため、バイオマスの使用がエネルギー問題を解決するわけではない、ということを理解する必要があります。
効率性がとても悪い
バイオマス発電は地球にやさしい発電として注目はされていますが、材料の運搬や乾燥などに手間とコストが大きくかかるにも関わらず、それほど大きなエネルギーとならないので、効率性がとても悪いです。
また、私たちが必要としている資源を使うということも反対です。動物の糞尿などはたくさんありますが、材木は有限であり、私たちの生活でもとても必要な資源です。
トウモロコシがよくバイオマス資源として考えられますが、今後食糧難が襲ってくるかもしれないといわれるほど、人口は増えていきます。その中で貴重な食料を使うのはどうかと思います。
私たちが生きていく中での優先順位を考えると、バイオマス発電をするべきではないと考えます。
先進国の自己満足
私がバイオマス発電に反対する理由は、地球規模での食糧危機問題が発生しているからです。バイオマス発電には主にトウモロコシが使われていると思いますが、現在、トウモロコシの消費割合は、バイオマス発電が多く占めています。
また、日本のスーパーに並べられているトウモロコシ、この値段自体も上昇しているのが現状です。つまり、バイオマス発電にトウモロコシを使いすぎて、世界でトウモロコシが不足しているという事です。
アフリカに目を向けてみましょう。アフリカでは、毎日多くの人が飢餓で亡くなっています。そのような貧しい人々も世界にいるにも関わらず、食料を使う。このような非道的な愚行はありません。
ましてや、バイオマス発電で得たエネルギーは、主に都市部で使われるのです。大量に作ったならば、貧しい人々に分け与える。これは人間として当たり前の良心とも言えます。
もちろんバイオマス発電によって世界のエネルギー問題が解決することもあると思いますが、それは先進国の自己満足だと思います。
食料品を使うのはよく考えるべき
バイオマスエネルギーの原料としては様々なものが考えられていますが、一番の問題は食料品を使う可能性があるということです。日本においては飽食の時代と言われて久しく、食べるものに困るということはありません。
しかし、世界的に見てみるとどうでしょう。食べ物が国民に行き渡らなくて困っているという国はごまんとあります。燃料なんかに使っている場合ではないのでは…と、そのような立場の人たちは思うことでしょう。
でも、日本にとっても実は他人ごとではありません。なぜなら日本という国は非常に食料の自給率が低いですからです。これだけたくさんの人口を抱えながら、多くの食料品を輸入に頼っているという状況は非常に危険です。
まともに自給できているのは米ぐらいです。それ以外がバイオマス燃料に使われてしまって、値上がりしたらどうでしょう。もしかして日本も食べ物に困る国に成り果ててしまう可能性も十分にあります。
そういった議論があまりされていない現状では、よく検討すべきだと思います。
まだまだ技術不足
バイオマス発電は、得られる熱量に対して使用するバイオマス量が多いと感じます。そのため、エネルギーを得るためにバイオマスを醸成させますが、それにコストやエネルギーが掛かりすぎます。
加えて、他の用途に使用すべき有用なバイオマス(食料や建材)をエネルギーに変換しようという動きも見受けられます。また、PM2.5の主要成分である有機炭素の発生源になりえるため、粗悪な設備では大気汚染を招きます。
このことから、バイオマスを作成してエネルギーを得るのではなくて、未利用の有機性廃棄物を利用でき、かつ完全燃焼できる(炭素を有機炭素として排出しない)ような設備を整備できるのであれば、バイオマス発電が可能であると思います。
しかし、雑多な有機性廃棄物では性状が不均一であり、得られる熱量が不安定になるだけでなく、ダイオキシン類を生成する触媒(例えば銅)なども含むことになるため、ある程度の高温で燃焼させなくてはいけません。
以上のことから、現状の技術ではバイオマス発電によるエネルギーの獲得は難しいと思います。
コストの割に見合わない
私がバイオマス発電に反対する理由は、その発電コストが高いという事です。太陽光、風力、水力などの他の再生可能エネルギーを使った発電に比べてコストが高いのが、バイオマス発電が普及しづらい原因になっていると思います。
太陽の光や風は、そこに自然に存在するもので、わざわざ用意しなくてもいいものです。一方、バイオマス発電の燃料として使う木材チップや家畜の糞尿などは、処分に困っているもの、余っているものではありますが、発電所まで運んでくる必要があります。
フードマイレージの発想でいうと、これは燃料マイレージといえば良いのでしょうか。バイオマス発電の燃料マイレージは高いという事になります。
その他、バイオマス発電は二酸化炭素を排出しない発電と言われていますが、それは言い方次第ではないかという疑問があります。
バイオマス発電の燃料として使う木材チップなどは「森林の木」として植えられていた時に二酸化炭素を吸収しています。その木材チップを燃やして発電することで二酸化炭素は排出されるのですが、木材のトータルの二酸化炭素の排出量としてプラマイゼロとなります。
なので、実質は二酸化炭素を排出していることになり、本当に環境に優しい発電方法ではないのではないかと思います。
経済的にも資源的にも疑問
まずは経済的な面で反対です。どう計算しても現在では火力発電や原子力発電の方がコストが安上がりです。
火力発電のように二酸化炭素も出ず、原子力発電所のように放射性物質も出ず、安全な発電だとしても、現在の社会ではコストが見合うだけの発電でなければ使えません。理想だけでは飯は食えないということです。
むしろ、太陽光発電や地熱発電に期待し、力を注ぐべきです。今後さらに科学技術が発展していけば、伸びていく分野なのでしょうけれども。
また、資源の問題もあると思います。バイオ燃料を使うわけですが、人間の食料ともつながる大豆やトウモロコシを使っているわけで、気候変動による資源量の変化は大きく、当然価格にも影響することでしょう。
木材をとなれば、当然森林の伐採となり、自然環境保護とのバランスの問題にもつながってきます。一部の大規模な施設が可能な先進国の考え方なのかなという気もします。経済的、資源的に苦しい国には果たして導入可能のなのか疑問です。
カーボンニュートラルの欠点
私はバイオマス発電に疑問を持っています。どちらかというと反対の立場です。確かにメリットはたくさんあると思うのですが、主に二酸化炭素について心配をしています。
バイオマス発電のメリットとしてカーボンニュートラルが挙げられていますが、それ自体は電気を作ることだけに関して適用されることではと考えています。
つまり、その燃料を発電所に運ぶまでに排出される二酸化炭素は考慮されていないのではということです。1度の運搬の排出量は微量かもしれませんが、それでも完全なカーボンニュートラルとは言えないと思います。
今後、バイオマス発電の量が増えれば、燃料がより必要になり、運搬量も増えることは明白です。そうなれば、微量だった運搬の際の二酸化炭素も、無視できない量にまで増えてしまうのではないでしょうか。
私は少なくともこの問題がクリアにならない限り、バイオマス発電には反対という意見は変わりません。早急にエネルギー問題が解決されることを望んでいます。
メリットに対してデメリットが大きすぎる
自分はバイオマス発電には反対です。
反対の理由としては、植物を始めとする生物由来の資源を燃料として使うために食用の作物栽培が減る可能性があるからです。食用の作物が減れば、自然と野菜や果物は価格が高騰していき、自分達のお金では食べれなくなるかもしれないからです。
あと、コストがかかりすぎる点も反対理由の1つです。発電所を建設するためのコストは当然かかりますが、バイオマスの収集作業にコストが意外とかかりすぎます。そして、集めたバイオマスの管理や加工をするのにも、コストがかかりすぎています。
この広くない日本の領地に、バイオマス発電ができるほどの十分なバイオ燃料があるのかと思います。十分に燃料を生産するには狭すぎますし、広めようとすれば山や熱帯雨林などを切り開かないとダメになります。そうなれば再生エネルギーの意味がありません。
確かにバイオマス発電はメリットも多いですが、デメリットの内容が大きすぎるので、自分はバイオマス発電には反対です。
食物の価格高騰を招く危険性
木材や農業廃棄物などのエネルギー資源は、炭酸同化作用によって太陽の光を吸収して空気中の二酸化炭素を増やしません。エネルギーとして利用する際に、燃焼などにより二酸化炭素が排出されますが、植林や農作業により大気中の二酸化炭素を吸収します。
このため、バイオマスを利用することにより、大気中の二酸化炭素が増加することはありません。確かに、化石燃料の代わりに利用すれば、二酸化炭素の排出を抑制できます。
しかし、発電を行うには発電所の建設、建築資材に関わる資材の運搬、送電線の設置、開発工事などの課程で大量の二酸化炭素を放出することになり、結果、大気中全体で考えた場合、発電所の建設が増えれば、やはり大気中の二酸化炭素量は多くなる可能性があります。
また、発電に利用するバイオ燃料の原料となる農作物をつくるために、森林を開拓するなど、結果的に自然破壊が進み、環境が悪化する可能性があります。
さらに需要が高まれば、野菜などを育てる農家が生産を切り替え、結果、食物が不足して価格高騰を招く要因にもなりかねません。このような問題点があるため反対です。