発電の仕組み
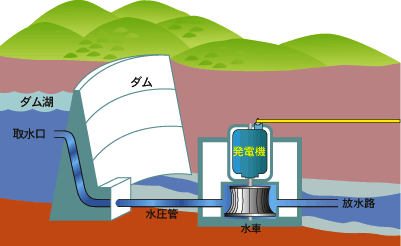
(出典:東北電力)
水を高い所から低いところに流して、その水の流れる力で発電用の水車を回転させるという仕組みです。落差さえあれば発電することができるため、多くの水力発電所は山間部に設置されています。
水力発電では水という枯渇の恐れがない自然のエネルギーを使っていて、さらに火力発電のように燃料を必要としないため、二酸化炭素や有害なガスを排出しません。
水力発電のメリット
上の表に出てきた各メリットについてかんたんに解説します。
再生可能エネルギーである
水力発電は水の流れという自然現象を利用して電力を生み出すため、石油や石炭のように有限な資源に頼らずに済みます。水は降雨や雪解けによって自然に循環するため、枯渇する心配がほとんどありません。エネルギーとしての安定供給が見込め、持続可能な社会の実現に貢献できます。特に気候変動対策として再生可能エネルギーの導入が求められている現代において、水力発電は信頼性の高い電源として位置づけられています。また、他の再生可能エネルギーと比べて出力が安定していることも大きな利点です。
CO2の排出がほぼゼロ
水力発電は化石燃料を燃やす工程がないため、運転中に二酸化炭素(CO2)をほとんど排出しません。これは地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制に非常に有効で、環境負荷の少ない発電方法とされています。火力発電と比べてCO2排出量が大幅に少なく、太陽光や風力と並んでクリーンエネルギーの代表格です。特に日本のようにエネルギーの多くを輸入に依存している国では、自国で環境負荷の少ない電力を生産できる点で水力発電の役割は重要です。将来の脱炭素社会への移行に向けて不可欠な要素といえるでしょう。
安定した電力供給が可能
水力発電は太陽光や風力のように天候や時間帯に大きく左右されることが少なく、比較的安定して発電できるのが特徴です。ダム式の場合、貯水された水を制御することで、必要なときに安定した出力を供給できます。また、季節や時間による変動があっても調整がしやすく、電力需要のピーク時にも対応可能です。発電の出力調整が比較的容易なため、電力網の安定運用にも寄与します。特にベースロード電源としてだけでなく、需給バランスの調整にも活躍する存在です。
運用コストが低い
水力発電所の建設には多額の初期投資が必要ですが、一度完成すればその後の運用・維持にかかるコストは比較的低く抑えられます。燃料を必要とせず、水の流れだけで発電できるため、燃料調達コストがゼロで済むのは大きな利点です。また、機械設備の耐久性が高く、長寿命化が進んでいることで頻繁な部品交換も必要ありません。自動制御装置や遠隔監視システムの導入が進んでおり、人件費も低減できます。結果として、長期的な運用では他の発電方式より経済性に優れた電源といえるでしょう。
寿命が長い
水力発電所は他の発電施設に比べて非常に寿命が長く、50年以上安定して稼働することが可能です。実際に100年以上稼働している発電所も存在し、設備のメンテナンスを適切に行えば非常に長期間にわたって活用できます。このような長寿命の発電施設は、長期的なインフラ投資として優れており、コストの回収期間が長くてもその後の収益化が期待できます。また、地域のインフラとして定着しやすく、災害時にも一定の信頼性を持つ発電所として評価されています。エネルギー政策上の安定性にも寄与する要素です。
電力の即時供給が可能
水力発電は、特にダム式や揚水式の場合、短時間で発電を開始・停止できるという利点があります。電力需要が急増した際にも迅速に対応できるため、ピークカットや緊急時の電力供給に非常に有効です。たとえば、地震などの災害時に電力が途絶えた際、水力発電所は比較的早く復旧し、重要インフラや病院への電力供給を支える役割を果たすことができます。また、再生可能エネルギーの出力変動を調整するための「調整電源」としても有用で、全体の電力系統の安定運用に大きく貢献します。
国内エネルギー自給率の向上
日本はエネルギー資源の多くを海外から輸入していますが、水力発電は国内の河川や降水を利用するため、自国の自然資源だけで電力を賄うことができます。この点は、エネルギー安全保障の観点から非常に重要です。世界的なエネルギー価格の変動や、国際的な供給リスクに左右されずに安定供給を図れるという意味でも、水力発電は戦略的な価値があります。また、山地の多い日本では地形を活かした中小規模の水力発電所の導入も進んでおり、地域主導型のエネルギー供給にもつながっています。
発電と水管理の両立が可能
ダム式の水力発電所は、発電だけでなく治水や農業・工業用水の供給、上水道の安定確保など、さまざまな水管理の役割を兼ねています。たとえば、雨が多い季節には貯水し、少雨時には放流量を調整することで水資源の効率的な活用が可能です。さらに、洪水時にはダムが緩衝帯の役割を果たして下流の氾濫を防ぎます。これらの機能を発電と同時に実現できるため、複合的なインフラとしての価値が高く、地域にとって多目的で有益な施設となります。
地域の雇用・観光資源にもなる
水力発電所やダムは、その建設・維持・運営の過程で地域に雇用を生み出します。特に過疎地や山間部においては、数少ない産業基盤として地域経済を支える存在です。また、ダム湖や周辺施設は観光資源として活用されることも多く、展望台、資料館、ダムカードなどの取り組みによって観光客を呼び込む効果もあります。地域イベントや防災教育の拠点となることもあり、単なるインフラを超えた地域コミュニティとの結びつきが期待できます。
蓄電代わりの揚水発電ができる
水力発電の中でも揚水発電は、夜間など電力需要が少ない時間帯に余剰電力を使って水を上の貯水池に汲み上げ、必要なときに下流に放水して発電する仕組みです。これは大規模な「電力の貯金箱」として機能し、電力需給の変動に対する柔軟な対応が可能になります。特に太陽光や風力のような出力が不安定な再生可能エネルギーとの組み合わせに最適であり、電力系統の安定化に大きく寄与します。大規模なエネルギー貯蔵技術として、今後の脱炭素社会において重要な役割を果たすと期待されています。
水力発電のデメリット
上の表に出てきた各デメリットについてかんたんに解説します。
建設コストが非常に高い
水力発電所、特にダムを伴う施設の建設には、数百億円以上の巨額な初期投資が必要になります。土地の整備、コンクリート構造物、発電設備、送電インフラなど、膨大な工事が伴うためです。さらに環境影響評価や住民説明、用地買収などの調整に時間とコストがかかり、計画段階から完成まで10年以上を要するケースも珍しくありません。このため、事業化に慎重な検討が求められます。初期投資の大きさから、採算が取れるまでに非常に長い期間がかかることも事業リスクとなります。
自然環境への影響が大きい
ダムの建設は川の流れをせき止めて貯水池を形成するため、周囲の生態系に多大な影響を及ぼします。特に魚類の回遊ルートを遮断し、生物多様性を損なう要因となることが多く報告されています。また、森林伐採による動植物の生息地の喪失、水質の悪化、温度変化なども懸念材料です。下流では水流が弱くなることで、堆積物の移動が減少し、河川環境が変化します。このような環境破壊が、地域住民や自然保護団体からの強い反対を受ける要因になることもあります。
住民の立ち退きや移転問題
大規模なダム建設では、貯水池に水をためるために周辺の集落や農地が水没するケースがあり、そこに住む住民には立ち退きや移転が求められます。このため、地域住民との間で強い対立や反発が生じることもあります。特に、古くからの集落や文化的価値のある場所が水没する場合、単なる生活環境の移転以上に大きな損失となります。補償や再定住支援が行われるとはいえ、元の暮らしを取り戻すことは容易ではなく、社会的・心理的な負担も非常に大きいと言えます。
適地が限られている
水力発電には落差と流量が必要不可欠であるため、発電に適した地形や水系を持つ場所は限られています。日本国内でもすでに多くの有望な地点は開発済みで、新たな大規模水力発電所を建設できる候補地は非常に少なくなっています。また、残された適地が環境保全区域や観光地である場合、開発のハードルはさらに高くなります。これにより、新規導入の余地が少ないという制約があり、再生可能エネルギーとしての拡大には限界があると指摘されています。
干ばつや水不足に弱い
水力発電は水をエネルギー源としているため、降水量が少ない年や長期的な干ばつが続くと、発電能力が著しく低下するリスクがあります。特に地球温暖化の影響で気候が不安定になっており、今後さらに水資源の確保が難しくなることも懸念されます。発電所の立地によっては、水不足により発電を一時停止せざるを得ない状況もありえます。水の安定供給に依存している点で、他の発電方式に比べて自然条件の変化に対して脆弱であるという弱点があります。
長期的なメンテナンスが必要
水力発電所は一度建設すれば長寿命で運用できるものの、維持管理には継続的な努力が必要です。特にダムには堆砂という課題があり、長年にわたって土砂がたまり続けると貯水容量が減少し、発電効率が低下します。これを防ぐには定期的な浚渫(しゅんせつ)作業が必要ですが、費用と時間がかかるため、実施が難しい場合もあります。また、水門やタービンなどの機械設備の摩耗や故障にも対応する必要があり、トータルでの運用コストは軽視できません。
建設期間が非常に長い
水力発電所の建設には長い時間がかかります。環境影響評価、住民との協議、用地取得、地盤調査、設計・工事など、段階ごとに時間を要するため、10年以上かかるプロジェクトも一般的です。そのため、短期的な電力不足への対応策としては不向きであり、即効性を求められる電力供給計画には使いづらい側面があります。また、計画の途中で情勢が変化した場合に、コストや需要とのズレが発生し、採算性に悪影響を及ぼすリスクもあります。
地震や災害リスクに脆弱
日本は地震大国であり、ダムが地震の影響で損壊するリスクは常に存在します。大規模な地震が発生し、ダムが決壊すれば、下流の地域に壊滅的な被害が及ぶ可能性があり、安全性の確保は極めて重要です。また、集中豪雨や土砂崩れによって貯水池が埋まる、または施設が損傷するリスクも高く、自然災害への対応力が問われます。設計段階での厳格な耐震性評価や、非常時の放流体制の整備が必要不可欠です。
発電効率が立地に依存する
水力発電の効率は、立地条件によって大きく左右されます。流量が豊富で落差が大きければ高効率の発電が可能ですが、そうでない場合は出力が極めて小さくなります。そのため、同じ設備投資をしても地域によって得られる電力量には大きな差が出ます。また、小規模な発電ではコストに見合った効果が得られにくく、事業採算性を確保するためには入念な事前調査が必要です。立地の選定が発電事業の成否を大きく左右する要因となります。
気候変動の影響を受けやすい
気候変動によって降雨パターンが変化すると、水力発電にも直接的な影響が生じます。例えば、豪雨が集中する地域と干ばつが続く地域の偏りが強まることで、水資源の不安定さが増し、従来のように安定した発電が難しくなる可能性があります。また、温暖化により積雪量が減少すると、春先の雪解け水に頼っていた発電所では出力の低下が予想されます。このように、長期的な気象の変化が発電量に影響するため、将来のエネルギー政策においてはリスク管理が必要です。
水力発電の種類(発電方式による分類)
水力発電には様々な種類のものがありますが、2通りの分類の仕方があります。まずは「発電の方式」によって分類するパターンをご紹介します。
流れ込み式(自流式)
川の流れをそのまま利用する方法です。
天候や季節によって流れる水の量が変化するため、発電量をコントロールすることは難しいです。ただ、この方式の発電所の建設にはコストがそれほどかからないというメリットがあります。
調整池式
川の流れをせき止めた規模の小さいダムに水を貯水することで水量を調節する方法です。
電力需要の小さい夜間には出力を抑えて、需要の大きい日中には出力を高めるなどといった具合に、出力をコントロールすることができます。
貯水池式
調整池式よりも大きなダムを使う方法です。
川を流れる水の量は季節的に大きく変化しますので、大きなダムに水を溜めておいて、その水を利用して発電します。電力需要の小さい春秋に水を溜めて、需要の大きい夏冬に水を流して発電するというケースが多いです。
揚水式
発電所の上部と下部にダムをつくって、上下のダムの水を揚げ下げして繰り返し使用する発電方法です。
日中の電力需要が大きい時間帯には、上部のダムから下部のダムへ水を流して発電を行い、需要の小さい夜間に下部のダムから上部のダムへ水を汲み上げて、再び日中の発電に備えます。
水力発電の種類(構造物による分類)
前述の通り、水力発電を分類する方法は2パターンあります。こちらの項目では「水力発電の構造物」によって分類した場合についてをご紹介します。
水路式
川の上流から水路によって水を発電所まで導いて発電する方法です。この方式は、前述の流れ込み式(自流式)と組み合わされるケースがほとんどです。
ダム式
ダムを作って人工湖を作り、そこで生ずる落差を利用して発電します。ダムの水位の変化によって落差変動が大きくなるのも特徴です。貯水池式・調整池式と組み合わされるケースが多いです。
ダム水路式
前述のダム式と水路式を組み合わせた発電方式です。ダムと水路により落差をつくります。貯水池式・調整池式・揚水式と組み合わされるケースが多いです。
日本の水力発電と世界の水力発電
日本と世界の水力発電に関する項目です。「世界と比較して日本の水力発電はどのような点が異なっているのか」「水力発電の世界シェアはどの程度なのか」など、簡単にまとめてみました。
日本の水力発電
明治時代から活用されている歴史の長い水力発電は、1960年代の高度経済成長期に入るまで、日本における発電の主流でした。
今でこそ火力発電が水力発電を圧倒するほどのシェアを誇っていますが、当時は「水主火従」と言われ、水力発電がメインでした。当時作られた仙台の三居沢発電所や京都の蹴上発電所などは、今でも水力発電を行っています。
大規模な水力発電に適した場所ではほとんど建設が完了しているため、これからは中小規模の水力発電所の建設が中心になります。
火力発電や原子力発電のように莫大な電力を生み出すことはできませんが、再生可能エネルギーかつクリーンエネルギーである水力は、これからも一定以上の割合で活用され続けて行くであろうことは間違いありません。
世界の水力発電
世界で最初に水力発電が行われたのは1878年です。イギリスで行われました。世界的に見ても日本と流れは同じで最初は水力発電が中心でしたが、その後は火力発電に主役の座を奪われるという形です。
現在では世界の総発電量の約15%が水力発電によって生み出されています。
国別に見ていくと水力発電の割合が比較的高いのは、中国・フランス・イタリアの3ヶ国です。それぞれ国内総発電量の10%前後を占めています。
日本では約7%ですが日本も世界的に見ると高い水準にあります。大国アメリカは約6%ほどです。逆に極めて割合が低いのはイギリスと韓国です。ともに1%ほどです。
日本では同じクリーンエネルギーである太陽光発電や風力発電や地熱発電などに注目が集まっていますが、世界的には発展途上国を中心に大量の未開発水力地点があるといわれていて、急ピッチで水力発電所の建設を進めている国も多くなっています。
これから発展途上国の国々が経済発展を遂げていく過程で、今よりもはるかに多くの電気需要が発生するのは間違いありませんので、それらの国々では水力発電による電力供給の割合も増加するのではないかと思います。
また、そこで作った電気を蓄えることができる大型の蓄電池の開発も重要となるでしょう。
推進派と反対派
水力発電は古くから日本でも行われている方式で、かつては火力発電よりも多くの電気を生み出していたこともありました。
現在は再生可能エネルギーということで、再び脚光を浴びていますが、日本ではダムを造れるような場所がもう限られているということもあり、これ以上の発展の可能性は少なそうです。
一方で、世界ではまだまだ水力発電に適している土地が残っているので、これからも数が増えていくのではないかと予測されています。
ダムを造る必要がある場合はどうしても自然環境を破壊してしまうため、反対の意見が挙がることも多いのですが、造った後は二酸化炭素も排出せず、地球環境に優しいというメリットもあります。
賛成意見
クリーンな水力発電
私は、水力発電はこれからもっと積極的に進めていくべきではないかと考えています。その理由としてあげられることが、水力発電は、二酸化炭素などを一切排出しない、クリーンな自然エネルギーであるからです。
つまり、二酸化炭素などの大気汚染物質を出さないということですから、地球環境に大きな悪影響を与えてしまうこともほとんどありませんし、水の落差を利用するだけで発電できるというところが評価できる点だと考えています。
小規模水力発電に期待したい
水力発電所は、地域水没・漁業への悪影響などを考えますと必ずしも環境に優しいとは言い切れません。また、新規のダム建造はコストが高くつくことを考えますと、安上がりでもないことが分かります。
しかし、ダム建造などを必要としない「小規模水力発電」には期待したいと思います。
これは、ビルなどで雨水や排水を利用して水車を回すもので、地域を選ばずに設置できる利点があります。保守が大変などの問題はありますが、環境にも良く、しかも安価です。太陽光発電よりも向いているのではないでしょうか。
全面的に支持したい
水力発電は有害物質を排出しないため、地球に優しい発電方法なので賛成です。原子力発電や火力発電は発電時に二酸化炭素を排出してしまいますが、水力発電は違います。地球温暖化が加速している近年では注目度が高いといえます。
加えて、再生可能なエネルギーでもあります。水なので何度も繰り返して使うことができるのでとてもエコです。
水はダム等で貯めておくことができるため、風力発電や太陽光発電のように天候に左右されることが少なく、安定して発電できるのもいいです。
また、他国から発電に必要な資源を輸入することなくできます。必要なのものは水なので、日本国内でまかなうことが可能です。そのため、コストも他の発電方法と比較するとかなり抑えることができ、経済的だといえます。
以上のメリットを考えると水力発電を全面的に支持したいです。
景観を損ねない
水をエネルギーにしているため、使い回しも容易ですし、何より安全なので信頼できます。有毒ガスや放射能なども発生せず、何処に設置しても景観を損ねません。水力発電の水車を観光名所にしている所もあるぐらいですから。
水力発電所を見学させてもらったのですが、巨大な水車がグルグル回る様子は見ていて飽きませんでした。子どもにとっても勉強になりますし、大人も疲れている時に水車を眺めれば癒やされます。以上の観点から全面的に賛成です。
ただし、水を汚さないこと、水場の生態系を脅かさないことが前提です。汚水を循環させても、見た目が悪いだけですからね。あくまでも水場は借りものです。きちんと水質管理をしたうえで、綺麗な水を発電に利用してほしいです。
地域に応じた発電方法
水力発電の良さは、再生可能なエネルギーを利用しているところと、温室効果ガスや有害物質などの大気を汚染する物質を排出しないところです。また、二酸化炭素も排出せず、クリーンな発電方法です。
そして、燃料を必要としないので、燃料の価格や諸外国との関係に左右されず、安定した供給を行うことができます。
水力発電は水さえ流れていれば24時間発電することが可能ですし、落差を利用しているので、水の資源が豊かで、かつ、山々が多い日本の地形に適した発電方法の一つと言うことができます。
また、大規模なダムを用いたの水力発電だけではなく、小規模の水力発電もあるので、地域に応じた発電方法ができるのもメリットです。
日本ではベスト
水力発電は電気の発生が安定していて、施設も長持ちするので賛成です。我が家の近くにも水力発電用のダムがあります。ダムの水位は安定していて、今までダムが枯れたことはありません。
ダムが作られた場所は山奥の上方で、誰も住んでいない場所でした。そこには細い道があるくらいで、人もあまり近寄らなかったです。
しかし、そこにダムができると道路が整備され、記念館も建ち、ダムを見渡せる公園もできました。半ば観光名所のようになったのです。そこは、いつも静かに水をたたえ、ちょっとした湖のように見えます。
静かに水を貯めているだけのダムは騒音も出しません。この静かな場所が電気を供給してくれるなんて実感が湧きません。空気も汚さず、完全に自然を有効活用したクリーンエネルギーです。
日本における水力発電は歴史が長いので、その技術も発達しています。公害がなく、電気が安定供給される水力発電は、今のところ日本ではベストだと思います。
地理的特徴をいかせる
私は水力発電に賛成の意見を持っています。賛成の理由の1つとして、日本の国土が持つ地理的特徴をいかして発電することができるという点です。
日本は山や河川がたくさんあります。水力発電は水が落ちる力を利用して発電しますので、この日本の国土が持つ地理的特徴を最大限にいかして発電できるのです。
私は発電方法がたくさんある中で、その国に一番合う発電方法を積極的に取り入れるべきだと考えています。そのため、水力発電には賛成であり、どんどん取り入れるべきであると思っています。
次に水力発電に賛成な理由の2つ目としては、「地球に優しい」発電方法だと言えるからです。私が言う「地球に優しい」とは、地球温暖化に繋がるようなガスなどを排出することがないということです。
火力発電は水力発電よりもたくさんの電力を作ることができますが、その分たくさんのガスを出しますから、将来的に地球温暖化などの問題に繋がりかねません。
また、原子力発電に関しても大量の電力を作ることができますが、放射能や放射性廃棄物の問題があります。
その点で水力発電が地球環境に与える影響は小さく、今後100年200年先の地球を考えると、発電方法の1つとして水力発電を進めていくべきだと考えています。
水力発電は欠かせない
日本は水に恵まれた環境にあるため、発電方法として水力発電は適したものだと思います。もともと地形的に山が多くあり、水力発電を行う環境としては有利な面があります。
今の状況下で新しいダムを作るというのは経済的にも立地的にも難しい面がありますが、今あるダムを今後も活用すれば、電力供給の助けになると思います。
それに水力発電の良さは、何と言っても自然に優しいことです。発電によって環境に影響を与えるような有害なものを排出することはないため、これからの地球環境を考えた上でも安心した発電方法と言えます。
災害の多い日本で、原子力発電の稼働はこれから廃止に向かっていくと思いますが、その中にあって水力発電のような再生可能エネルギーは重要度がますます増してきます。その中の一つとして水力発電は欠かせないものだと思います。
持続的な先を見据えた発電方法
日本は山、そして水が大変豊かな国なので、水力発電は適当なエネルギー確保の方法だと考えます。
一番いいのは、もともとあるものを効率よく使用できるという点です。環境を破壊することなく、自然の力を借りてエネルギーを生産する、理想的な方法だと思います。
初期費用こそかかりますが、ほかの環境破壊を伴う様なエネルギー生産の方法よりも持続的ですし、なにより安心して使用し続けられる方法だと思います。
水力発電のような、持続的な先を見据えた発電方法などにこそ、税金を使用してでも力を入れていくべきではないでしょうか。
これからは技術が発展して、もっと簡単に小型の水力発電も行えるようになる見通しですので、どんどん導入していくべきだと考えます。
小規模発電もどんどん推進していくべき
水力発電所はメリットが多い発電方法なので賛成です。水力発電は化石燃料などを使用しないため、枯渇することがないというクリーンなエネルギーであり、原子力発電のような大きな事故が起こりにくいということがメリットの1つです。
また、ダムに付随する水力発電であれば、風力発電や太陽光発電のようなほかのクリーンな発電方法と違い、水力発電を保有する会社が発電をしたいというときに集中して発電できるということが、ほかのクリーン発電に比べて優れている点だと思います。
その他、水力発電は水が上から下へ落ちるエネルギーを利用するので、山が多く、水資源に恵まれた日本の地形にあう発電方法であります。
そういったこともあり、ほかのエコエネルギーの発電量が、日本の総発電量の1%前後のなか、水力発電は日本の総発電量の8%をしめており、現在日本では欠かせない発電方法であります。
今後も技術改良により、川や潮といった小規模発電ができるようになると予想されるため、推進していくべきだと思います。
再生可能エネルギーの中でも特に安定している
私は、電力の安定供給が出来るうえに、発電効率がいい水力発電に賛成します。太陽光発電など自然の力を借りて発電する自然発電には、発電量が低い、発電が安定しないというデメリットがありますが、水力発電に限っていえば、そのデメリットがありません。
発電においてもっとも大切なのは、天候や周囲の状況に関わらず、きちんと一定量の発電が出来ることですが、水力発電はこの条件を満たしています。その上、発電量そのものも多いのですから、発電方法としてはいう事がありません。
その発電システム上、水の上に作らないといけない(つまり作られる場所が限られる)というデメリットがありますが、それを考慮しても、非常に優れた発電方法だと言えるでしょう。
原発事故により、原子力発電所を増設する事が難しくなった無資源国の日本にとって、水力発電は必須の発電だと言えます。何の資源もいらないのに、安定して電気を手に入れることが出来る発電方法、それが水力発電です。
なので、これからの日本は水力発電に力を入れていくべきでしょう。
クリーンでエコな発電
水力発電については以下に挙げる理由で賛成です。
まず、資源の少ない日本において、比較的潤沢にある水資源という再生可能エネルギーを利用するからです。山やダムも多いので、落差を利用して発電する仕組みもこの国に向いていると思います。
次に、他の再生可能エネルギーと比べて、水力は水流のエネルギーを電気エネルギーに変えるので変換効率が良い、つまりエネルギーロスが少ないエコな発電方法と言えます。
それに、電気は貯めて置けないので、ダムの放水等を利用した場合、電気需要が高まる時期に集中して発電したりするなど、発電量が比較的調整しやすい発電方法であることもメリットとして挙げられます。
最後に、発電することで発生する副産物、たとえば原子力発電で言う核のゴミ、火力発電で言う二酸化炭素はじめとした温室効果ガス、酸性雨や光化学スモッグの原因となる化学物質などを排出しないという点でも賛成できます。
日本に最適だと思います
水力発電は非常にクリーンなエネルギーで、日本に向いている発電方法だと思います。日本は起伏の多い土地で、高いところから低いところに水が流れるという位置エネルギーを有効に活用できると思います。
また、火力発電や原子力発電のように何かを買ってきてエネルギーに変えるわけではありません。日本ならそれほど水不足の心配をすることもないので、太陽光や風力ほど環境に左右されることもないのです。
また、太陽光や風力で発電するとなると、発電機を作らなければならないので、発電ができなければこまります。しかし、水力発電はダムを作るときに一緒に作ればいいわけで、発電以外にもダムという役割もあり、一石二鳥になるわけです。
安定供給できるというのは、生活から切り離すことのできない電気だからこそ、最大の魅力ではないでしょうか。
それに、二酸化炭素なども出さないのでとてもクリーンですし、日本という国土や気候などにも最適と言えると思います。台風や大雨さえも水力発電的に言えばプラス要因になりうるのです。
エコで観光資源にもなります
水力発電はエコな発電方法で、問題が少ない方法だと思うので賛成です。
水力発電を行う時にはダムが必須なので、当然建設コストは高く、村や山などがいくつもつぶれてしまうのは大きなデメリットです。
しかし、出来上がってしまえば、その後数十年にわたって継続的に使えますし、治水や貯水も行えるので副産物のメリットが結構大きいと思います。
加えて、ダム湖は大きな観光資源にもなりますので、水上公園を作れば新たな憩いの場が広がりますし、公共事業で作られる設備としては結構役立つのではないでしょうか。
もちろん作りすぎる必要はありませんし、一つ一つの発電量が少ないのは問題だと思いますが、同じくCO2を排出しない原子力発電との併用が最も効果的だと思います。
また、他の発電方式と比べて、施設の耐久性やメンテナンスの簡単さもメリットと言え、トータルで見ればその分のコストは浮いているのではないでしょうか。個人的には釣りが好きなので、新たな釣りスポットが増えるのもメリットの1つです。
人の健康に被害を与えない
水の力は強いです。津波を見ても、すごい力を持っていることはよくわかります。その水の力を使って、水力発電を行うことは素晴らしいことだと思います。
発電時に、地球に悪影響を与えるものは排出されません。温室効果ガスを排出しないので地球温暖化対策になります。将来のことを考えると、地球のためにも子供たちの将来のためにも優れた発電方法です。
日本は山がたくさんあるので、水力発電は向いています。小さな発電であれば、川や用水路を使っても発電できます。経済的に見ても、他の発電方法よりもコストを抑えることができます。
どの発電方法にもメリットデメリットはあります。しかし、この水力発電は、人体に影響を与えないというメリットが最大の賛成理由です。今あるダムを大いに活用して、水力発電を盛りあげていってほしいです。古くなっても、補修工事をすればまだまだ使えるはずです。
日本の地形に最も適していると思います
私は今の日本に水力発電は必要不可欠だと思うので賛成です。日本は森林の国です。日本の河川は、長さこそ短いものの、その高低差は世界でも希なレベルです。この高低差を利用した水力発電は、日本の地理的にも最も適した発電方法だと思います。
実際に北欧フィンランドでは、その土地の立地を生かした水力発電で100%電気をまかなっています。日本も100%までとは不可能だとしても、原子力発電の危険性を考えると、もう少し水力発電による発電量を増やす方向を考えてもいいと思います。
水力発電は、あまり知られていませんがエネルギー変換効率がどの発電方法よりも一番良い発電方法です。水力発電は液体の水がタービンを回すことで電気を発生させます。
原子力発電・火力発電・地熱発電など、これらの発電方法は水を加熱して発生した気体がタービンを回すために、そのエネルギー変換効率がそれほど良い発電方法ではありません。なので、私は日本に地理に適していて最もエネルギー変換効率が良い水力発電に賛成です。
超小型水力発電にも期待してます
自分は水力発電は賛成派です。エネルギー資源に恵まれているとは言えない日本には、山や川が多くあり、水の流れを利用して電力を生み出す水力発電は適している国だと思うからです。
あと、他の再生可能エネルギーを利用する発電方式と比べるとコストが安く済むという特徴があります。
なにを言っても温室効果ガスを排出しない、光化学スモッグや酸性雨と言った大気汚染の原因となる酸化物を排出しないといった環境に優しい水力発電はこれからの地球温暖化を食い止めるには必要な発電方法だと思います。
水力発電は落差のあるダムを利用して、水を下に流して発電用の水車を回すという仕組みが最も一般的です。ダムを造ることが必要なので、ダムの費用や周辺地域の自然環境を破壊してしまいますが、山の起伏が大きい日本には向いている発電方法だと思います。
あと、超小型水力発電もあるので、用水路や小川などでも発電できます。改良していったら、いつか家庭でも水力発電できるようになるかもしれないですね。
水資源が豊富な日本だから水力発電を推したい
水力発電に全面的に賛成です。これまで電力供給の主流であった原子力発電所の危険性があらためて認識されるようになり、将来の子どもたちに残していくものとして不安を感じています。
この世界に生きているのもとして、処分のできない危険なゴミや事故を起こす可能性のある原子力発電にいつまでも頼っていてはいけないと思います。原子力発電に代わるものとして、自然エネルギーを利用した水力発電は、これから増えていって欲しい存在です。
水力発電は、電力会社だけでなく一般に人々にも発電に参加しやすいというメリットがあると考えています。
例えば、田畑の用水路を利用した簡易水力発電や下水処理施設を利用した水力発電が増えていると聞いたことがあります。電力会社のように大きなダム等をもっていなくても発電ができるのです。
日本は水資源が豊富な国です。至るところに水が流れています。個人家庭や各自治体が、小さな水力発電を利用するようになれば、ゴミのでない素晴らしい世界になるのではないかと思います。
反対意見
漁業にダメージが出る
日本近海での漁獲高は減少傾向にありますが、その理由には海洋汚染の他に水力発電所の建造も考えられます。なぜかと言いますと、魚のエサになるプランクトンを育てるための栄養分が河川から海に流れ込まなくなったからです。
ダムができたことにより、それらの栄養分がダム湖の底に沈んでヘドロになり、養分欠乏と水質悪化の原因となっております。
漁業関係者の間では昔から「魚は山から来る」と言われていましたが、水力発電所によって魚は山から来なくなり、彼らは沖合や遠洋での操業を強いられているのです。
生態系への影響が心配
私は、水力発電には反対の立場です。
確かに水力発電は、待機を汚さないクリーンなエネルギーとして評価することが出来るのですが、一方で、自然の川をせき止め、ダムを作って発電することが多いため、その流域の水の流れを変えてしまうことになります。
そうなると、今までそこにあった生態系を脅かしてしまうかもしれないということが懸念されるのではないのでしょうか。そのような細かいところにも気を配って考える必要があると思っています。
これ以上はダムを造るべきではない
山の高低差を利用した自然にやさしいような発電のように見えますが、ダムを開発しなければならない点で自然に良い発電とは言えないと思います。
ダム開発のために、広範囲の自然を破壊しなければならないような発電方法は環境も破壊するし、今まで維持していた景観も破壊してしまうため、これ以上増やすべきではないと思います。
もう作ってしまった所は元の自然環境に戻すのは不可能だし、作ったとき以上の費用もかかってしまうので、これから水力発電をすすめる場合は、もっと自然を破壊しない水力発電の方法を見つけて進めて欲しいと思います。
ダムはこれ以上作れない
私は水力発電には反対したいと考えています。日本には高低差のある山が多く、さらに川も多いので、水力発電には適しているところだと言われています。しかし、一見メリットと思われるこの話が、逆に今はデメリットになっていると思います。
日本は山と川が多い利点を利用して、水力発電のために多くのダムが作られてきました。しかし、日本はどちらかと言えば、大陸面積の小さい島国だと言えます。
そのため、水力発電のためのダムはこれ以上、作れない状況になっているはずです。これからは水力発電以外の発電方法を、考える時期に来ていると思っています。
また、最近はゲリラ豪雨という局所的な雨の降り方が多くなっています。局所的なゲリラ豪雨が多いと、ダムに水がたまりにくいのではないでしょうか?この先の時代の変化を考えると、水力発電には反対したいです。
生態系や生活を奪う
水力発電は、ダムを作ることによって周辺の生態系を変えてしまうため、反対です。
たとえば、ヤマメが泳いでいるような清流や、夏になると様々な昆虫が大合唱をする里山も水の底に沈めてしまいます。これにより生態系は失われます。生活は、人間のせいで一変してしまいます。
また、水力発電は、動植物の生活だけではなく、人間の生活も奪ってしまいます。ダムの建設により、故郷を追われ、違う土地で生活しなければならなくなった人もいます。
たとえば、高知県の早明浦ダムは、元々あった村を、ダムの底に沈めてできています。そのため、貯水率が下がると、ダムの底にある、役場や民家が顔をだします。
渇水の象徴と言われますが、補償があったとしても、もともとあった生活を奪った代償は大きいと思います。
水力発電は、再生可能エネルギーとして注目されていますが、生態系や生活を奪うものであるため反対です。
人命に関わることも
ダムを建設しての水力発電には反対です。ダムの建設自体が河川流域の環境破壊の一因となっていて、生態系への悪影響も大きいからです。
堰き止められた水は必ずどこかで淀みが発生することとなり、水質が悪化します。この水質が悪化した水がいずれは放流水を通じて環境に悪影響を与えることが懸念されます。
また、ダムには治水の観点からも問題があると考えています。世界的に異常気象が増えていますが、日本においても各地で集中豪雨が頻発しており、豪雨による直接的な水害のみならず、ダムからの緊急放水による被害も見られます。
経済的な損失のみならず、人命に関わることも少なくないため、ひとたび被害が発生すると社会的な損失は計り知れません。
堤防の拡張なども行われているものの、設計時の想定を超えた増水などに至ることが常であり、イタチごっこです。結局、自然のチカラにはかなわないと思います。
推進には反対
水力発電の新規の開発を進めることには反対です。環境とコストの観点から、エネルギー政策に占める水力発電の割合は現状維持に留めるべきです。
水力発電は大規模なダムによって行われています。ダムの開発には山間部を切り開いていく多大な労力とコストがかかります。それらは、公共事業の形で国の税金で行われます。
現在のひっ迫する国庫財政状況の中、多大な出費を伴うダム開発及び水力発電の新規開発は財政負担を増大させます。
また、開発によって日本の豊かな山間部の自然と景観が失われてしまいます。一度開発してしまった自然は、もう二度とその姿を取り戻すことはありません。
環境とコストの観点から、水力発電の推進には反対します。これまでの施設の活用に留めるべきです。
ダムは永久的に使えるものではない
水力発電を行うためにはダムが必要で、ダムの建設のためには広範囲の森を伐採し、ダムに変えなければいけません。
自然の森の中に人の手が大きく加えられることによる自然環境、生態系への影響もありますし、一度破壊してしまったものを100%元に戻すことはほぼ不可能です。
また、現在は水分量は豊かな場所でも、昨今の異常気象等を考えると、今後、降水量が極端に少なくなったりして安定した供給を行える保証もありません。
逆に大雨等によるダムの決壊などのリスクもありますので、二次災害、三次災害につながる危険もあります。
そして、ダムは永久的に使えるものではないので、使われなくなったダムはどうするのか、次のダム次のダムと、ダムを造り続けていくのかなどの課題もまだまだあります。
環境を破壊してしまう
水力発電の最大の弱点は、発電効率です。他の原子力発電や火力発電に比べて、発電にやたらと手間がかかるにもかかわらず、得られる電気量は少ないです。これでは国民のすべての電力をまかなうなど、到底無理な話であるといえます。
水力発電所を建設するためには、ダムを造らなければなりません。そのために山の木々が伐採され、環境を著しく損ねてしまいます。
水力発電は環境にやさしいという意見がありますが、ダムを建設するために環境を破壊してしまうので、決して環境にやさしいとは言えません。
環境にやさしい発電法と言えば、太陽光発電や風力発電があり、これらの発電方法が近年台頭してきているので、水力発電のメリットは今やないといっても過言ではありません。
他の発電方法に頼るしかない
水力発電は、自然エネルギーの代表です。安定して電力を供給できるので、昔から日本各地で造られています。ですが、現在では発電が可能な土地が残っていません。
新たにダムを造ろうとしても、日本国内には条件のいい場所がありません。使い尽くしているのです。小さなダムならできても、それでは効率が悪くなります。
そして、水没する土地が使えなくなる問題もあります。ダムの貯水池は他の用途には使えなくなります。これからはダムを造れそうにないです。現在あるダムを継続して使い続けるしかありません。
水力発電が伸びる余地がないので、新規に建設することは不可能です。古くからあるダムが壊れたら、そこを修理して使うことができても、新規立地はできません。新たに発電所を建設できないなら、他の発電方法に頼るしかありません。
安全性・安定性がよくない
水力発電については、非常にクリーンな再生可能エネルギーとして考えられているものの、発電効率や安定性および安全性、そして環境配慮の面で反対します。
日本の国土の多くは、平地よりも山岳地帯が多く、水力発電所のためにダム建設が行い易いことがあります。しかし、ダム建設をする際、膨大な建設費用が発生することや、建設時の安全性、すなわち作業者の労働災害防止に問題があります。
また、空梅雨などにより、ダムが干上がることで発電能力が失われることもあります。そして、電気と水という点においては相反するものであり、台風や集中豪雨によりダムの発電システム並びに開閉システムの機能が水没により、失われる危険性があります。
特に、東日本大震災後に東北電力が管轄する水力発電所は、2011年6月に発生した大雨により、発電能力を失い、復旧に膨大な期間を要しています。
また、水質によっては、酸性度の高い地域ではコンクリートの耐久性が損なわれ、維持費用が嵩むことがあります。確かに、水力発電所かつ揚水型発電を行っている場合、安定した面がありますが、長期運用による安全性確保では明らかに経済性が悪くなります。
また、地形を変えることで多くの生物の生態系が失われる他、予想しない事故が発生する可能性があります。万が一、老朽更新をしない場合、ダム下流域にある住宅街には多大な被害を与える可能性があります。
電気を使う発電方法
水力発電は再生可能エネルギーと言われています。確かに、ナイアガラの滝のように、あれぐらい大量の水がコンスタントに流れる川があれば、その下にタービンを置いて発電することで相当な発電量になると思います。
しかし、日本の河川の水量はそこまではありません。だから、実質水力発電といっても山頂からふもとにかけて水の管を滑り台のように設置して、そこに水を流すことで水力発電を行っています。
そして、流れる水の量が少ないときは下に流れた水をくみ上げて、山頂まで電力を使って運ばなくてはなりません。なので、水力発電はかなり電気を使用する発電方法ということになります。原子力発電や火力発電などに比べてコスパが悪い発電ということです。
原子力発電で作られた電気は電気使用量の少ない夜間には余っている状態です。その余った電気を水力発電の水をくみ上げることに使うことで、原子力発電と水力発電がタッグを組んだ形になっています。
その原子力発電ありきの日本の発電方法の一部に組み込まれている水力発電には、私は賛成できません。
ダムの今後が不安
水力発電は主に川の水の水力を利用してタービンを回し電気を作ります。そのためにはダムが必要です。ダムは雨水を溜め込んで洪水を防いだり、飲み水や水田などの農業に使われますが、主な目的は発電です。水力発電にはダムは不可欠なのです。
しかし、このダムによって川の環境は変わります。土砂までダム湖でせき止め、下流には流れません。下流の河原は痩せて雑草が生えています。
少雨の夏は電力を作るため、ダム湖の水位が減っても電力用に底の汚れた水を使います。そのため、少雨の夏は清流といわれる川もほこりっぽい汚れた川になってしまいます。また、増水してダムが水を放流すると、ドロの混じった汚い水が流され、下流の川底にどろが溜まります。
逆に冬場は水力発電もあまりいらないので、川の水位がぐっと減り、干上がったような川になってしまいます。
さらにこんな酷い発電もあります。四国の大河の上流に発電用の堰堤があります。その堰堤の水を、ひとつ山を越えた別の川の発電所に流し、電力を作っているのです。つまり、発電のために大河の水を別の川に流しているのです。そのため、この川はいつも極端に水が少なく、雄大な流れが貧疎な流れになっています。
川のダムの水を利用する水力発電は自然破壊に繋がります。また、ダムにも寿命があります。老朽化したダムを一旦破壊すると、ダム湖に溜まったヘドロが完全に流れ、元に戻るには何十年もかかるといわれています。
今あるダムの今後はわかりません。発電する為に片っ端から作ったダムのしっぺ返しが来る日はそう遠くないと思っています。
経済面でも環境面でも合理的でない
日本だけでなく世界的に研究開発が行われているのが再生可能エネルギーです。これは、自然に優しいエネルギーとして将来を有望視されています。
その中でも、水の流れの力を利用してエネルギーを生み出す方法のことを水力発電といいます。ダムや水車をイメージするとわかりやすいでしょう。環境に優しいとは言いますが、果たして本当でしょうか?
ダムのような巨大な施設を建てるためには広い土地が必要になります。人が住むところに建てるわけにはいきませんから、山間部を切り開いてその広大な土地を利用するのです。この時点で既に自然破壊につながります。それまで森で暮らしていた動物の住処がなくなります。
更に、水力発電で生み出せるエネルギーは、火力発電や原子力発電に比べればどうしても低くなってしまいます。水力発電の施設を建てるまでにあらゆるデメリットがあるのです。他の発電方法に研究費を投じたほうが経済面・環境面で効果的ではないでしょうか。
生態系への影響が大きい
私は水力発電には否定的です。というのは、生態系を脅かしてしまうのではないかという懸念からです。
水力発電の問題点は、ダムの建設をしなければならない点にあります。たしかに水力発電は高いところから低いところへ水が流れることによる高低差で水車を回して発電するため、環境に優しいと思われがちですが、それは水力発電の一側面しか見えていません。
水力発電をするためにはダムの建設が必要と書きましたが、そのほとんどが、森林を伐採してダムを建設するため、周囲の生態系を脅かしてしまう危険性があります。短期的には電力が賄えていいかもしれませんが、長期的に考えると必ずマイナスに働きます。
それは、もしかしたら今生きている私たちがもういない頃になるかもしれませんが、それなら良いと考えるのは、あまりにも後世に対して無責任ではないでしょうか。
さらに長期間経過すると、ダムの底には土砂がたまり、発電量が減ってしまうという負の効果もあります。長い年月が過ぎたあとには、荒れた生態系と、使い物にならないダムを残していいのでしょうか。水力発電を推進しようとはどうしても思えません。
環境破壊を起こす
環境面から水力発電に対して反対します。まず、水力発電を作るにはダムを建設する必要があります。日本には、既にたくさんのダムがあります。ダムを建設するには既にある森林をたくさん伐採しなければなりません。
ただでさえ、温暖化によって世界全体が砂漠化しています。異常気象が増えて、このままいくと地球は滅びるという意見まであります。自然を維持することで、温暖化を防いで人間にとって最適な環境を提供してくれます。作物を実らせることが出来ます。ですから、環境破壊の面から言っても水力発電に関しては反対です。
また、水力発電は天候にかなり左右されます。ダムに水が貯まらなければ、発電に十分な放水が出来ないため作動しません。時に水不足が続くことがあってダム内の貯水量が少ないときがあります。異常気象で雨が降らない時期が続くことも考えられます。
このような不安定な要素の中で、環境を破壊してまでわざわざ作る必要があるのか大いなる疑問です。
超小型水力発電ができれば…
自分は水力発電は反対です。理由は、ダムや発電所を作る際、森林伐採をして自然環境を破壊してしまうからです。
「水力発電は二酸化炭素を排出しない」「光化学スモッグや酸性雨などといった大気汚染の原因となる酸化物が排出しない」とは言われますが、自然破壊の観点から、環境にはいいとは言いがたいです。ダム建設にも莫大な費用がかかるので、そこも問題です。
山が多く、起伏の大きい日本は水力発電には向いているかもしれませんが、今の日本国内には新たに大型ダムを作るのは困難です。ダムを建設して故郷が水没してしまった人もいると思います。そう考えるとどうしても水力発電はいいとは言えないです。
あと、長年使っていると、ダムの底に土砂が溜まってしまって発電量が落ちます。雨の降る量によって左右されやすいのも欠点です。安定的して電気を供給できないのに、中途半端に開発だけするのはいかがなものかと思います。
以上のことから、自分は水力発電には反対です。ただ、超小型水力発電で家庭でも発電できるようになったらいいですけどね。
自薦環境への負担が大きい
水力発電は、発電をする上ではクリーンなエネルギーですが、発電所を建設するのは自然に負担が大きいため反対です。
ひとたびダムを建設してしまえば、長期的に水の力だけで発電を行えます。しかし、その一方で大規模な森林伐採を行わなければ建てることができません。しかも、ダムの作成の為だけに道を整備しなければならず、伐採範囲は広範囲にわたり、環境への負担を大きくします。
また、日本の場合には大規模なダムの建設が難しく、仮に水力発電を推進していった場合には、全国に中小規模のダムが乱立する可能性もあります。しかも、安定的に発電できるわけではなく、降水量で発電量は変化する上に、長期的な使用でダムに砂利などが溜まり、発電量は年々減少してしまいます。
元々は、クリーンエネルギーとして注目されているのはいいのですが、結局のところは多大な負担を環境に強いているのが現状だと思います。日本の生態系の保全を考えても、水力発電は望ましいとは思えません。
ダム建設に公共事業費を使いすぎ
水力発電所はCO2排出もなく、他の発電方式に比べて危険性や発電機メンテナンスのコストが少ないなど、メリットが多い発電方式です。しかし、発電量の少なさはやはり問題で、水力発電で不足している分を火力で補っている現状です。
しかしながら、もっと問題なのは、やはりダムが乱立し、公共事業費がどんどんかかることだと思います。
ダム自体は治水や飲み水確保など必須な施設ではありますが、その必要もない場所へのダムの無駄な建設が多く、たいして発電量が見込めない場所であるにもかかわらず、公共事業だからという理由だけで中止にもならず、ダムが増加していくのが悪い点です。
昭和のバブル期に計画されたダム建設が、必要がなくなったにも関わらず続けられている例はたくさんあります。
魚やその他水生生物、植物への影響も大きく、水力発電の拡大という理由以外で建設されるダムにはストップをかけなければなりません。
結局、発電量が見込める場所への適切な発電所の建設と、不足している分は原子力発電で補い、火力発電を減らす。この道筋しか温暖化対策にはならないと思います。